豊橋市立豊岡中学校へようこそ!

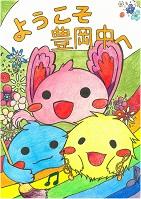
マスコットキャラクター
『サンバード(挨拶・歌・ボランティア)』
豊橋市立豊岡中学校のホームページへようこそ!
今年度、76年目の歩みを始めた豊橋市の東部に位置する学校です。学校や学区のさまざまな情報を、家庭や地域に発信して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。


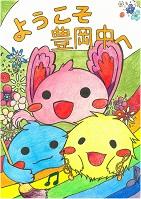
豊橋市立豊岡中学校のホームページへようこそ!
今年度、76年目の歩みを始めた豊橋市の東部に位置する学校です。学校や学区のさまざまな情報を、家庭や地域に発信して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
・令和7年度年間行事予定(3.12現在)を掲載しました。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |