
豊橋市立磯辺小学校




本日2月20日(金)8学級で学級閉鎖を行います。
インフルエンザの感染拡大予防のため、以下の8学級を臨時休業とします。引き続き感染拡大予防にご協力をお願いします。
1年1組、1年2組、1年3組、3年1組、3年2組、4年1組、4年2組、4年3組





















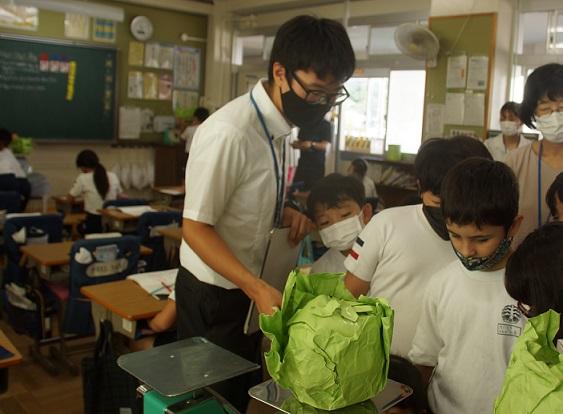




磯辺小コミュニティ・スクール
・「ニコニコ会」(ボランティアチーム)のご案内
神野新田干拓(4年生HP)
・isbgood - 神野新田干拓 (jimdofree.com)
豊橋市南陽中学校 (toyohashi-c.ed.jp)
豊橋市立小中学校情報ネットワーク
豊橋市立小中学校情報ネットワーク (toyohashi.ed.jp)
おうちで学ぼう!NHK for School | NHK for School
ユネスコスクール
ユネスコスクール 公式ウェブサイト | (mext.go.jp)
とよはしアーカイブ 豊橋市図書館のデジタル資料の検索、閲覧
ADEAC(アデアック):デジタルアーカイブシステム (trc.co.jp)
とよはし学校給食チャンネル
とよはし学校給食チャンネル - YouTube
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |