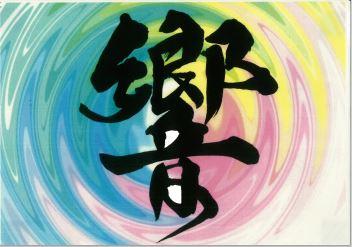2022年10月の記事一覧
南稜祭
初日はオープニングと合唱コンクールがありました。
オープニングでは生徒会による劇や全校アートのお披露目がありました。合唱コンクールではこれまでに練習してきた曲を一生懸命歌い,学級の団結力やつながりの強さを感じることができました。そして,特別支援学級の「スマイル」の発表では,今まで練習してきたダンスを披露し,そのダンスを3年生が一緒に踊り,大いに盛り上がりました。







2日目は午前中に体験講座が行われ,午後からは有志発表がありました。
体験講座では地域の方々や保護者の方に講師をお願いし,学校生活では経験できない素晴らしい体験をすることができました。有志発表では,今日まで練習してきた出し物を全校の前で披露し,個性豊かな発表や特技を生かした発表に大きい声援や拍手を送るなど大いに盛り上がることができました。






体験講座では保護者の方をはじめ,多くの方のお力によって無事終えることができたことを,この場を借りてお礼申し上げます。
PTAによるミニバザーでは,南稜ファイルやタオル,制服を販売し,26,300円の売り上げがありました。ありがとうございました。
1年生梅田川現地調査





10月19日(水),1年生が総合的な学習の時間に梅田川の現地調査に出かけました。川の水をバケツで採取し,パックテストを用いて水の汚れのめやすとなる「COD」「亜硝酸態窒素」「りん酸態りん」の濃度を測定しました。その結果,「亜硝酸態窒素」と「りん酸態りん」の濃度から【やや汚れている水】,CODの濃度から【汚れが多い水】と判定されました。また,川岸にはペットボトルや発泡ポリスチレンなどのごみが大量に落ちており,出前授業で聞いた海ごみの悲しい現実を目の当たりにしました。ごみ拾いをはじめると,とても1日では拾いきれない量に,生徒もショックを受けていました。そんな中,葦の間に小さなカニがたくさんいるのを見つけ,捕まえた生徒は「このカニを守っていくためにも,僕たちが梅田川をなんとかしくてはいけない」と話していました。学びの多い1日となりました。
2年生出前授業「みんなが防災マンになる授業」
10月14日(金),2年生の総合的な学習の時間に出前授業「みんなが防災マンになる授業」を実施しました。「どのような防災対策をすることが必要か」や「災害が起きたときに,自分たちにできることは何か」という疑問を解決するため,生徒たちは講師にお招きした豊橋市役所防災危機管理課の職員のかたの話を真剣に聞きました。「地震が発生したとき,家具の固定などの防災対策がされていないとどうなるのか」を検証した映像を見たときには,あまりの被害の大きさに驚きの声があがりました。また,南海トラフ地震が発生した際の,豊橋市の死者数や建物被害の状況予測では,4小学校区ごとの被害予測も発表され,自分たちの身近なところでも被害が起きることを理解しました。「自分の命は,自分で守る」「自分から声を出して動く」ことの大切さを学び,防災に対する意識を高めることができました。
【授業後の生徒たちの感想】
・40年以内に90%の確率で大地震がくると言われているので,今のうちから防災対策をしておくことが大事だと思いました。
・自分たちの住んでいるところでも災害の被害があるので,災害が起きたときのために家族としっかりと話しておこうと思いました。
・自分の命も大切だけど,周りの人の命も大切なので,中学生の自分でもできることを頑張ろうと思いました。



1年生出前授業「海ごみについて」




10月14日(金),1年生が総合的な学習の時間に出前授業「海ごみについて」を実施しました。「梅田川に落ちている大量のごみはどこからきたのか」「マイクロプラスチックとは何か」という疑問を解決するため,生徒たちは講師にお招きした愛知県環境局資源循環推進課の職員さんの話を真剣に聞き,「愛知県の海ごみは,内陸部で出たごみが,川などを流れて海にたどり着いたものが多い。南稜校区の梅田川は河口部に位置し,潮の満ち引きによってごみが海と川の間を行ったり来たりしている。」ことを学びました。「海ごみをなくすために,みなさんは何ができるでしょうか」という講師の問いかけには,多くの生徒が挙手をして発言し,環境問題に対する意識の高さが感じられました。今後は水質調査や生物調査を行いながら,梅田川の生態系を未来に残すために自分たちにできることを考え,実践していきたいと思います。
【生徒の考えた海ごみをなくすためにできること(一部抜粋)】
・いつでもごみ拾いができるように,ビニル袋をかばんに入れて持ち歩く。
・買い物をするときには,本当に必要なものか考えてから購入する。
・ごみを捨てた人を見つけたら,そのごみを拾う。
・魚が食べても問題ない素材でトレイなどを作る。
・バスケットゴールのように,ついついごみを入れたくなるごみ箱を設置する。
・ごみのポイ捨てに関する法律を強化する。
・ローカル番組や新聞で海ごみのことを伝える。
・マスコットキャラクターをつくり,TVやイベントで訴える。